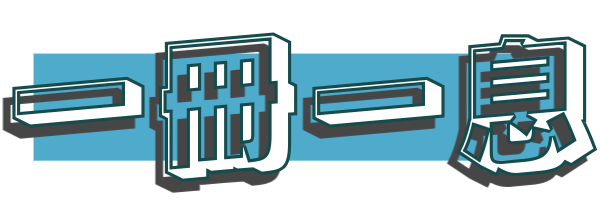【変身】朝起きたら虫になっていた男の不条理文学
| 著者 | 出版 |
|---|---|
| フランツ・カフカ | 新潮文庫:1952/07/28 |
Franz Kafka
ユダヤ人の商家としてプラハで生まれ、法学を修めた後、役人として勤めながら執筆活動。人間存在の不条理を主題とするシュルレアリスム風の作品群を残した実存主義文学の先駆者。
あらすじ
カフカの代表作となる中編小説。カミュの「ペスト」同様に実存主義文学かつ不条理文学といえます。
変身
ある朝、グレーゴルが目をさますと自分が巨大な毒虫になっていた。鎧のような堅い背、褐色の腹、たくさんの足、ねばねばした分泌液。
まだ夢の中ではと思ってもうひと眠りしようとしても、慣れない虫の体のせいでうまく眠りにつけない。
こんな異常事態でありながらグレーゴルが考えていたことは、外交販売員としての仕事の苦労のことだった。すでに汽車に乗る時間を逃してしまい、仕事に遅刻することが確定している。
時間に心配した母と父が起こしに来るがうまく返事ができない。相手の言語は解るが、こちらから発声して伝えることはできない。
グレーゴルは日ごろの習慣により、部屋の戸締まりはきちんとしていたので、家族が様子を見に来てもとりあえず部屋にこもってやりすごせる。
虫になった体でどうにかベッドから起き上がり、仕事に向かう支度をしなければ。
引きこもり生活
ついに職場の支配人が訪ねてきた。「体調が悪い」と適当な問答をして場をしのごうとするが、ついに両親と支配人たちが鍵屋を呼んでこじあけようとする。
なんとか自力で扉をあけて姿を表すと、母は絶句、父は臨戦態勢、支配人は恐怖のあまり逃げ出してしまう。
支配人に状況を取り繕ってもらうために、グレーゴルは追いすがろうとするが、その恰好が襲おうとしているかのように勘違いされた。父が棒でグレーゴルを追い立て、虫の姿で自室に引きかえすしかなかった。
今後もこのような誤解が生じ得るので、うかつに行動できない。
そうしてグレーゴルの自室でのひきこもり生活が続く。
リンゴ投擲
家族はグレーゴルが虫になっていることを理解してるものの隔離。本人は家族に迷惑をかけないようにひっそりと暮らす。そうして互いに牽制し気を使い、虫であることを受け入れながら共生していた。食事や掃除などグレーゴルの身の回りの世話は妹のグレーテが担っていた。
グレーゴルの体は次第に虫に順応していき、まず食の嗜好が変わっていった。新鮮な食材が食べられなくなり、腐ったものを好むように。いつの日か部屋中を虫の体で縦横無尽に這いまわるのが得意になった。
しかし心配なのは家族の経済状況だ。一家の大黒柱だったグレーゴルが働きに行けず、いまや家計は貯えを切り崩す生活。現状では2年食いつなぐのがやっとのところ。
家族はグレーゴルの部屋の家具をすべて撤去する話を持ち出す。すなわちグレーゴルが人間に戻ることをもう諦めたかのような決断に妹は強く反対していたが、結局すべての家具を片付けられた。
家族の中で母だけグレーゴルの変身を受け入れられず、これまでずっと彼の姿を目にしないように生活していた。ある日、グレーゴルの姿を目の当たりにした母がパニックを起こし、その様子から父がグレーゴルにりんごを投げつけると見事に背中に命中し、彼は重傷を負ってしまう。
グレーゴルの居場所
そして最終章へ。
リンゴの負傷で体の自由が制限され、事件以来グレーゴルの部屋の掃除は放っておかれるようになり、家族たちはもうグレーゴルがいなくても歩んでいけるような道へ進もうとしてる。
グレーゴルに頼らなくても経済的に生活していけるよう仕事を始めたのだ。
また、家の空き部屋を3人の紳士に貸し出し、家賃収入まで得るようになった。しかしこの紳士たちと家族を巡り、グレーゴルの居場所がなくなる事態へと発展していく。
最期にグレーゴルが選んだ選択とは…。
感想・書評
まずとにかくシュールな設定が目を引きます。
ベッドから起き上がるだけでも相当な時間がかかり、そんな状況にグレーゴルは自分でもおかしくなって笑っちゃってます。
そして虫になったまま、仕事に行かねばと焦っている点。どうしてこの状況を素直に受け入れているのか、もっと気にすることがあるだろうにと思って仕方ないですね。
この本を読み解いていくと、虫になったこと、それ自体には意味を持たせていません。だから最後まで虫になった理由も何も説明がなく、その状況が当たり前かのように淡々と進行していきます。
そして個人的にはグレーゴルの健気な性格に少し心を痛めます。こんな不条理に見舞われても、仕事のこと、家族のこと、そしてお金のことなど、彼は常に他者のためを想っていました。両親の借金を肩代わりしながら、やりたくない仕事を続け、広い家に住まわせている孝行ぶり。妹の音楽大学のための学資まで工面していました。
それが虫になってしまったばかりに、家族に気を使って怯えながら生活し、人間としての尊厳は急速に失われていく。逆に虫として扱われることに慣れていき、自尊心なんてあったもんじゃないでしょう。
彼の世話役を買っていた妹の心情も複雑です。慕っていた兄が突如虫になり、家族の中で自分しか世話をしない。最初はそんな微妙な気持ちで世話をしていたのが、次第にグレーゴルを虫を飼っているかのような対象として捉えだす。そんな妹の狂気のようなものが見え隠れします。
虫の姿について
このグレーゴルが『なんの虫』になったか、これはあらゆる議論がありますが、基本的には特定の虫を想定していないようです。作中でもグレーゴルは極力他人に自分の姿を見せないようにしているので、客観的な彼の姿を表している描写はありません。
グレーゴル自身の動きからさっするにムカデか、ゴキブリか、コガネムシなどいくつかの憶測はありますが、具体的な言及はされていません。確かなのは硬い外殻があること、毒があること、粘液を分泌することなどですね。
作者のカフカ自身、作品としても虫の姿を見せて読者にイメージを固定化させるのは避けたかったようです。その根拠に彼は、扉絵や挿絵に絶対に虫の姿を描かないよう要求していました。
一説によると虫の姿を固定化させない理由に、読者に想像を拡大できるようにしてるのではと思われます。
例えば、もし変身していない前提で状況だけを整理すると、グレーゴルは家族を養いながらしたくもない仕事を続ける重圧からノイローゼになった、とも捉えられます。虫になったか否かだけを取り除けば現実にあり得る話で、まるでグレーゴルにふりかかった事故のように思えます。なにせなぜ虫になったのかといった問いは一切なく、誰も気にせず、それこそふいに日常を襲う不条理性を描いているようです。
それでも生きていかなければならない、ここに本作の実存主義的な意図が見えます。
実存主義と不条理
虫になったことが事故だと前述しましたが、これもまた現実に置き換えられます。
例えば不慮の火災で顔を火傷して醜い姿になったとする。この容姿に対する不条理な事故という点において、虫になろうが、顔を火傷しようが、その原因や本質を追求しても仕方ない。事実は事実とただ受け入れて今を生きるしかありません。
これが実存主義。
実存は存在そのもの、本質はその存在が作り上げる目的や意義だが、起きた事故に目的や意義なんてありません。
これらの理解を広げていくと、人間というのは本質をもたずにこの世に産み落とされるものだと思えます。本は知識を与えるために書かれるし、時計は正しい時間を刻むために生産されます。人間もなにか運命や使命に定められていると思われるでしょうか。しかし人間は自分の未来を選択する能力があります。
「何のために生まれてきたのか分からない」なんて悩みは多いが、本質を伴わないまま右往左往しながら生きていくから、誰もが常に不安をかかえているのです。逆に言えば何にも縛られない自由であるということ。
人生において常につきまとう不安から逃れるために目的や意味を求めるのではなく、自身の自由な意志と選択ををもってして主体的に生きるのです。
当然その自由には責任も伴うが、だから生きるのは楽しい。そう哲学者のサルトルは言っています。
この実存主義的な思想で、不条理に抵抗していくさまを文学に落とし込んだのがカフカの変身。そして前回紹介しているカミュのペストでした。