左利きの人なら気にせずにはいられないタイトル。そして多くの左利きが「天才タイプなんだね」「器用だね」といった言葉を投げかけられてきたことでしょう。
しかし「左利き=天才」なわけではありません。右利きとは異なる脳の使い方によって、同じ経験から感じることとアウトプットする内容も変わるため、大多数とは発想が違うということになる。これが左利きの人が特異な目で見られる所以でしょう。
また、基本的に世界は右利き中心のデザインなので、右利きのツールや設計を快適に利用するための試行錯誤が求められる場面も少なくないです。それが結果的に左利きの人の脳のバランスを向上させ、器用だねと言われる人が多いのかもしれません。
このような左利きのすごさを脳科学の観点を交えて考察されています。

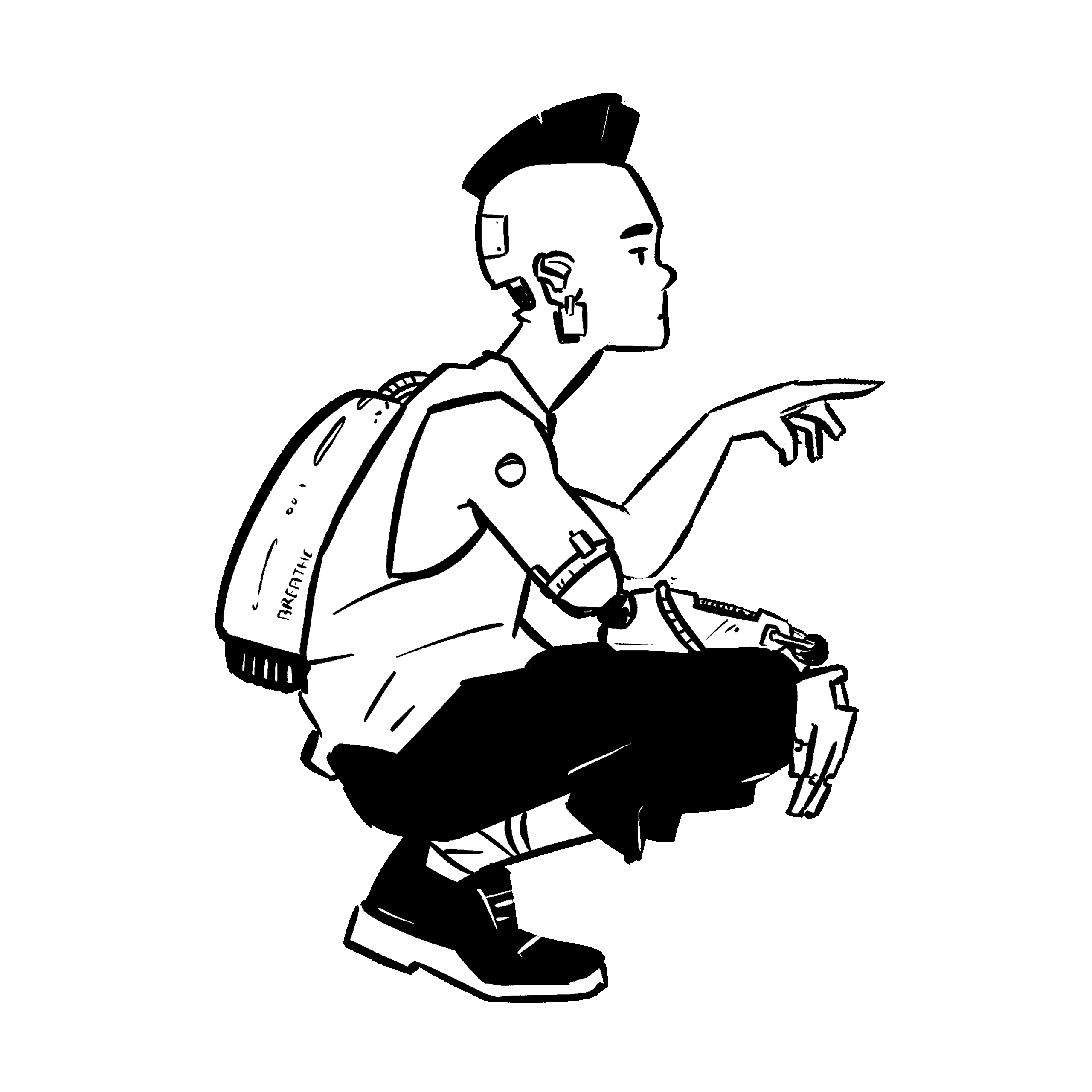
加藤俊徳
脳内科医・医学博士・加藤プラチナクリニック院長・株式会社「脳の学校」代表 世界700カ所以上の施設で使われる脳活動計測「fNIRS(エフニルス)」法を発見。
ダイヤモンド社2021年9月28日
脳番地による8つの仕組み
著者は「脳番地」という独自の見解に基づき、8つの脳の仕組みを定義しています。
脳番地
- 思考系
- 伝達系
- 聴覚系
- 理解系
- 感情系
- 運動系
- 視覚系
- 記憶系
これらはそれぞれが独立しているわけではなく、一つの動作に対して相互連携して働きかけます。
同じ細胞でも役割が異なり、感情系でも左脳は自分の感情や意思を作り、右脳では他人の感情を読み取る働きをします。要するに左脳は言語系情報処理、右脳は非言語系情報認識を得意とします。
しかし運動系は左右対称の働きで、利き手と反対側の脳がよく発達する傾向にあるようです。
多くの左利きは右利きの人より、脳をバランスよく使うために左脳がつかさどる言語処理へのルートが少し遠回りになる傾向にあります。つまり言いたいことのイメージは先行するけど、言葉がつながってこないという現象が起こりやすい。
左利きの人の主な特徴
左利きならではの特性や思考がいくつか挙げられていますが、とくに特徴的なものが以下の3つ。
- 優れた直観力
- アイデアと独創性
- ワンクッション思考
左利きの人が生まれてくる確率は両親の遺伝によります。
- 両親が右利き 9.5%
- 片親が左利き 19.5%
- 両親が左利き 26.1%
しかし、利き手を決定づける遺伝子はまだ見つかっておらず、現段階では遺伝に加えて生後の環境の影響があると考えられています。
直感に優れている
直感は単なる衝動ではなく、無意識下の膨大な脳の情報ベースから導き出している結論であることがあります。この潜在的な思考の結論が、論理的結論より良い結果をもたらす場合があります。これは論理的思考をベースにしたAIにも真似できない人間ならではの強みです。
左利きの多くは情報のイメージ保存がデフォルト。浮かんだことを意識的に右脳から左脳に移して、あえて言語化することで直感を形にして残すことができるようになります。もしあなたが左利きならメモを持ち歩くことを推奨されます。
豊かなアイデアと独創性
左利きは目で捉えた情報をイメージで記憶する傾向にあります。左脳で理論的にとらえると情報サイズは小さいが、右脳でとらえたイメージは情報サイズが大きいです。情報量が多くなるので、既成の枠に収まらない発想に繋げられるでしょう。
これを有用なものにするには、イメージ記憶情報を左脳に移して言語化する意識をもつこと。
コピーライト分野でも論理的な文章は右利きのほうが得意ですが、左利きはイメージを一言で表すような独創的な言葉を生み出すポテンシャルを秘めています。
ワンクッション思考
はじめはゆっくり理解するけど、コツをつかむと爆発的な応用力をつけるのがワンクッション思考。
右脳と左脳をつなぐ神経線維の太い束「脳梁」を介して頻繁に行き来する脳の使い方が影響しています。つまり両脳を刺激する機会に恵まれた左利きは脳を強くしているともいえます。
※右利きは左脳を多く使い右脳を眠らせてることが多い。
また、左利きはアウトプット速度が遅い傾向が見られました。並列情報である右脳を介して左脳にアクセスする特性に由来しておりワンクッションのラグが生じるからです。脳の瞬発力がないと悩む人も多いですが、これを解決するには脳の視覚系脳番地を鍛えることが効果的。
言葉を耳から聞いて行動に移す力と、その場の状況を目で見てから動く力の二つの脳の瞬発力があります。言葉は最後まで聞かないとすぐに動けませんが、視覚情報であれば瞬時に対応できます。具体的にいえば、とにかくしっかりと見て観察する力を意識すること。表情と顔色やしぐさ、道の途中の綺麗なものの発見、普段しない行動から得られる新しい体験などを、視覚系情報と結びつけるなど。
この鍛え方を応用して「見て真似させる」という行為が左利きの人の成長速度を高めるでしょう。
最強の左利き
左利きはもっと積極的に右手を使ってみてもいい。
左脳を刺激して物事を対比して考える力を養えるようになる。また人間は不自由な環境にあるほど創意工夫をこらして能力を伸ばす傾向にある。
左利きの特性から両方の脳を活用しやすいというのが大きなアドバンテージである。
書評
よく言われていることでもありますが、右利き優位の左脳は言葉や計算、論理的思考、による直列思考が得意。対して左利き優位の右脳は様々な情報が同様に浮かぶ並列思考の脳です。
左利きの人が左脳を鍛えるにはToDoリスト作成、日記をつける、ラジオを聴く、ブログやSNSで発信するといった言語化につながる活動が有効です。中でも外国語の勉強は脳番地をフル活用して左脳を成長させる最も効果的な方法です。単語の意味を覚えるために記憶系、感情系、思考系で文章をつくり、運動系を用いて書いたり話したり、伝えたいことを整理するために伝達系も活用します。
多くの左利きの人はこれまでの人生経験からも、両方の脳を活用しやすいという大きなアドバンテージを有しています。初めは不自由に感じるかもしれませんが、その不自由さから創意工夫をこらして積極的に右利きとなることで、最強の左利きになれるとされていました。
私自身も左利きでありながら、ツールによっては両利きのものがあるので、本書に書かれている両脳活用の希望の兆しは想像できます。積極的に右手(左脳)を使って両利きを目指すのは、脳科学的な観点から優秀な思考力を得るための新たなアプローチかもしれません。
実際問題は忙しい多くの現代人が、思考力という目に見えない成果の為に、両利きを目指そうなんてばかげたことは実践しないと思います。しかし右利き優先デザインの世の中で、左利きの人が強いられてきた小さな苦労は、両脳を刺激して優秀な脳の使い方をしてきたかもしれないという、自己理解を深めるきっかけにはなったかもしれません。

すごい左利き|加藤俊徳
1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き 「選ばれた才能」を120%活かす方法
ダイヤモンド社



