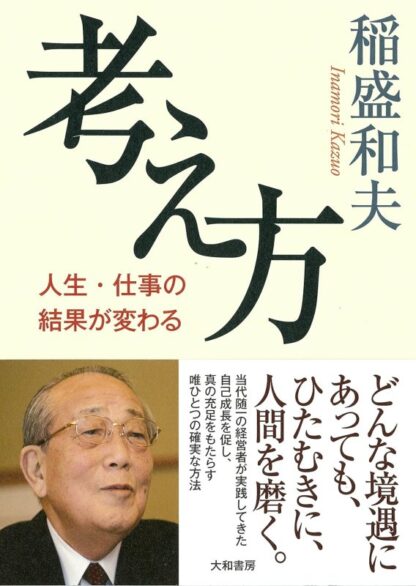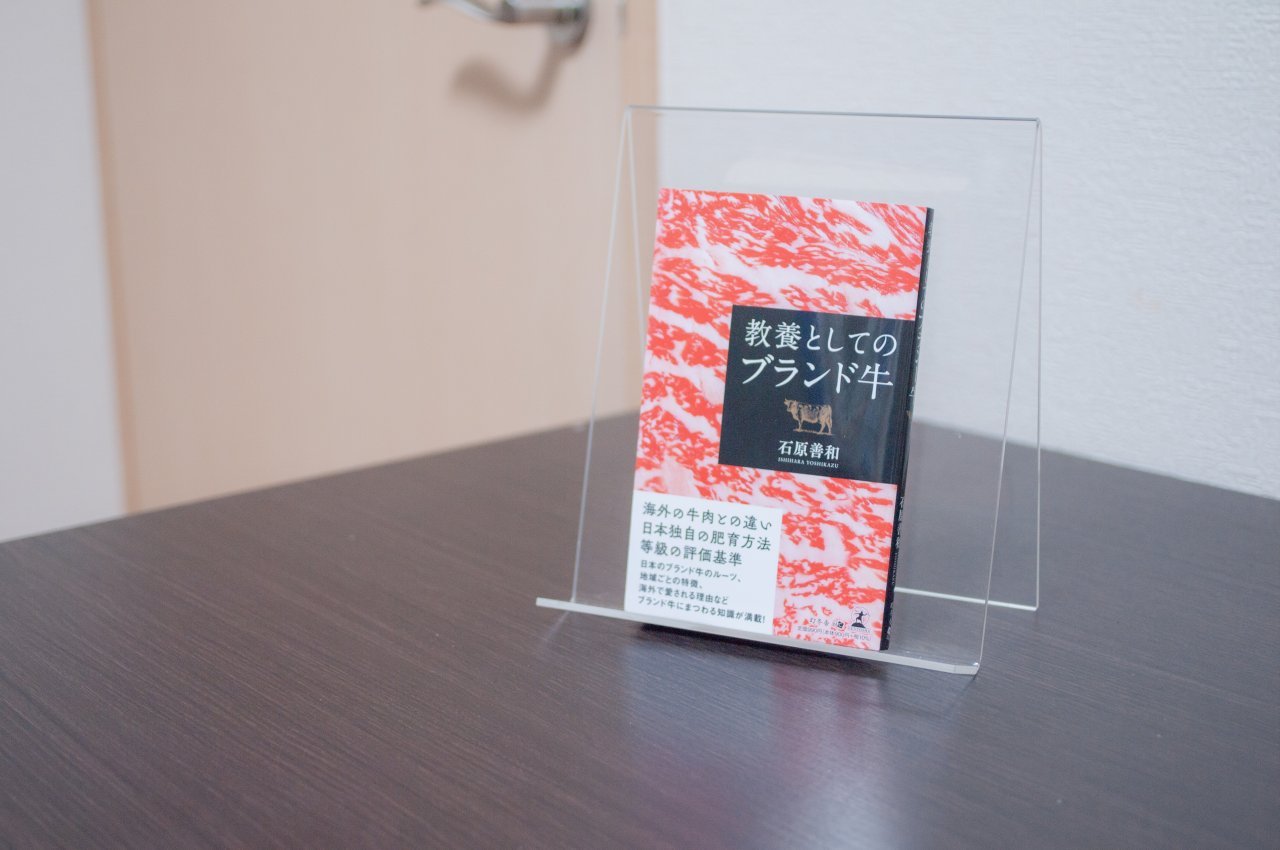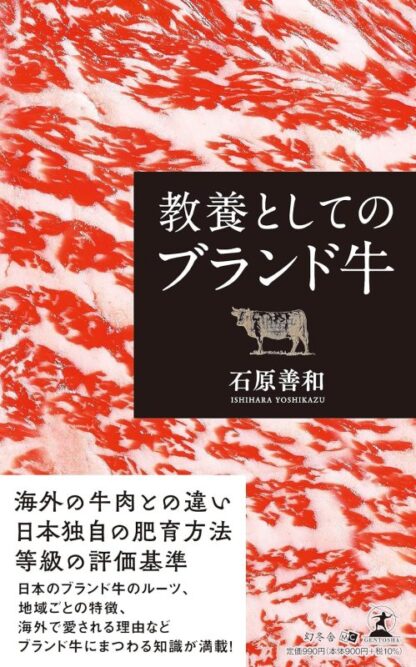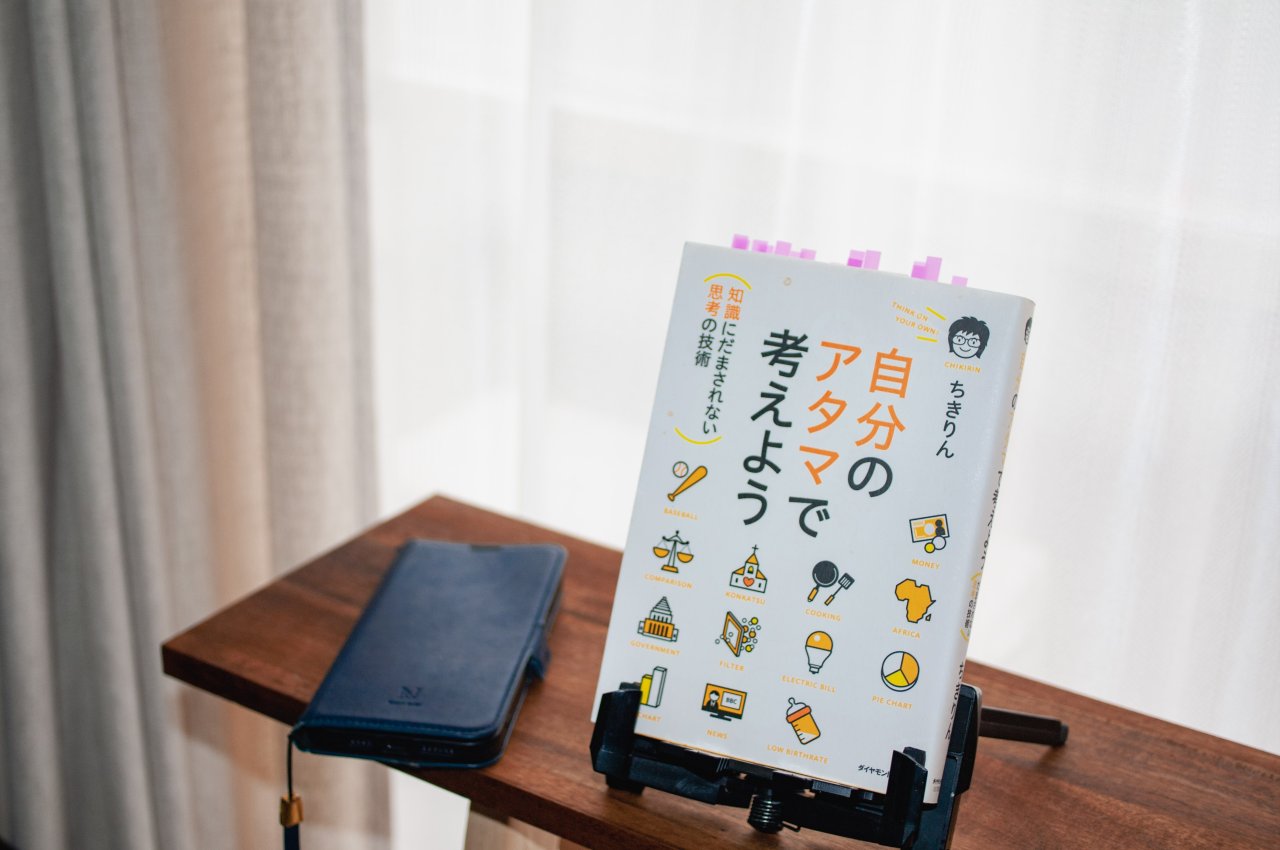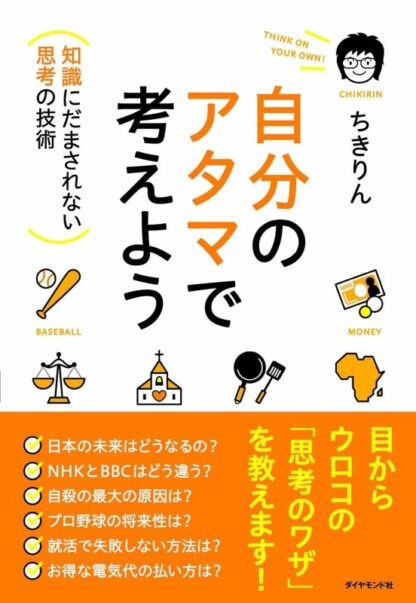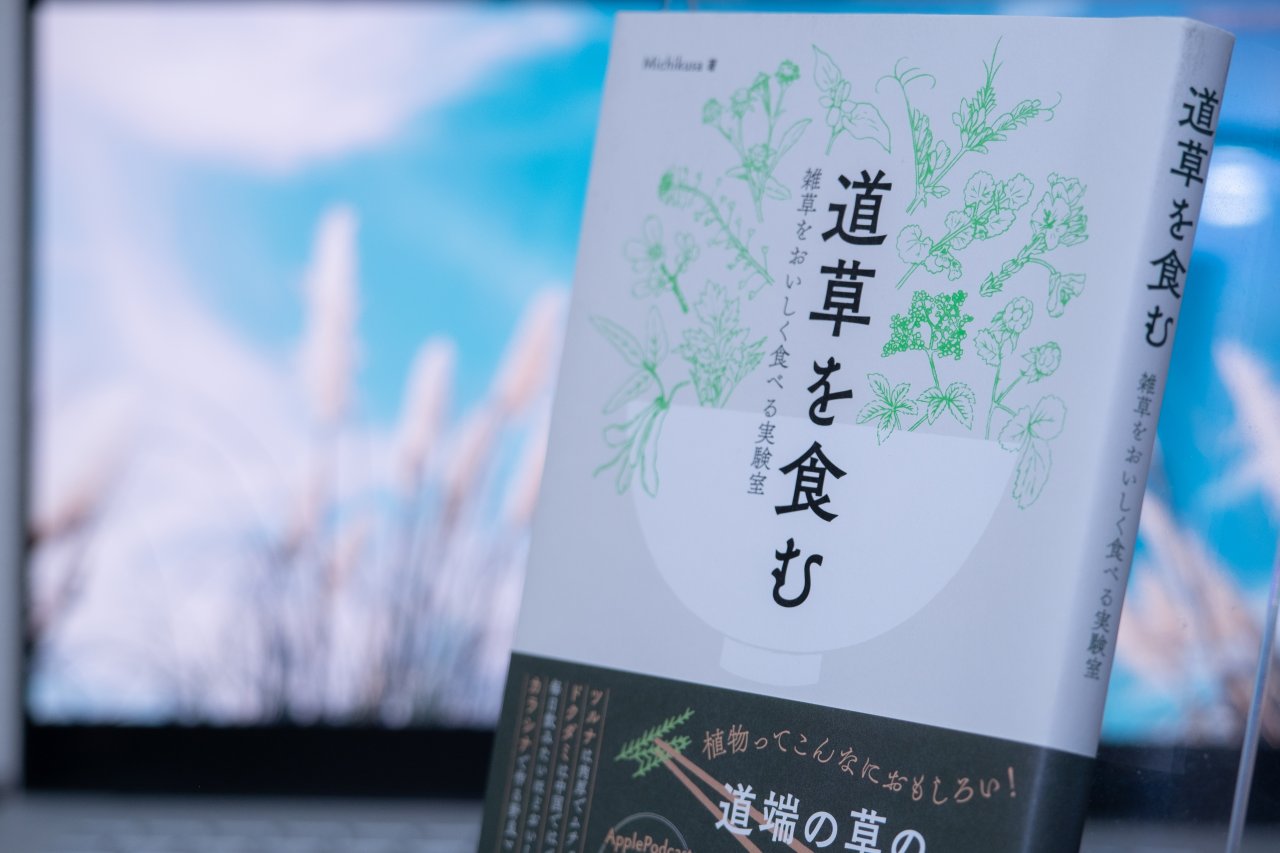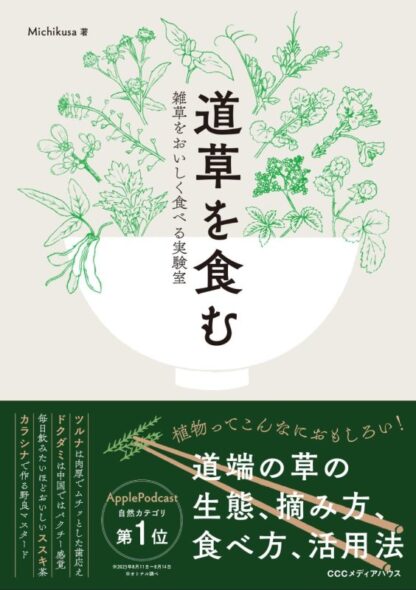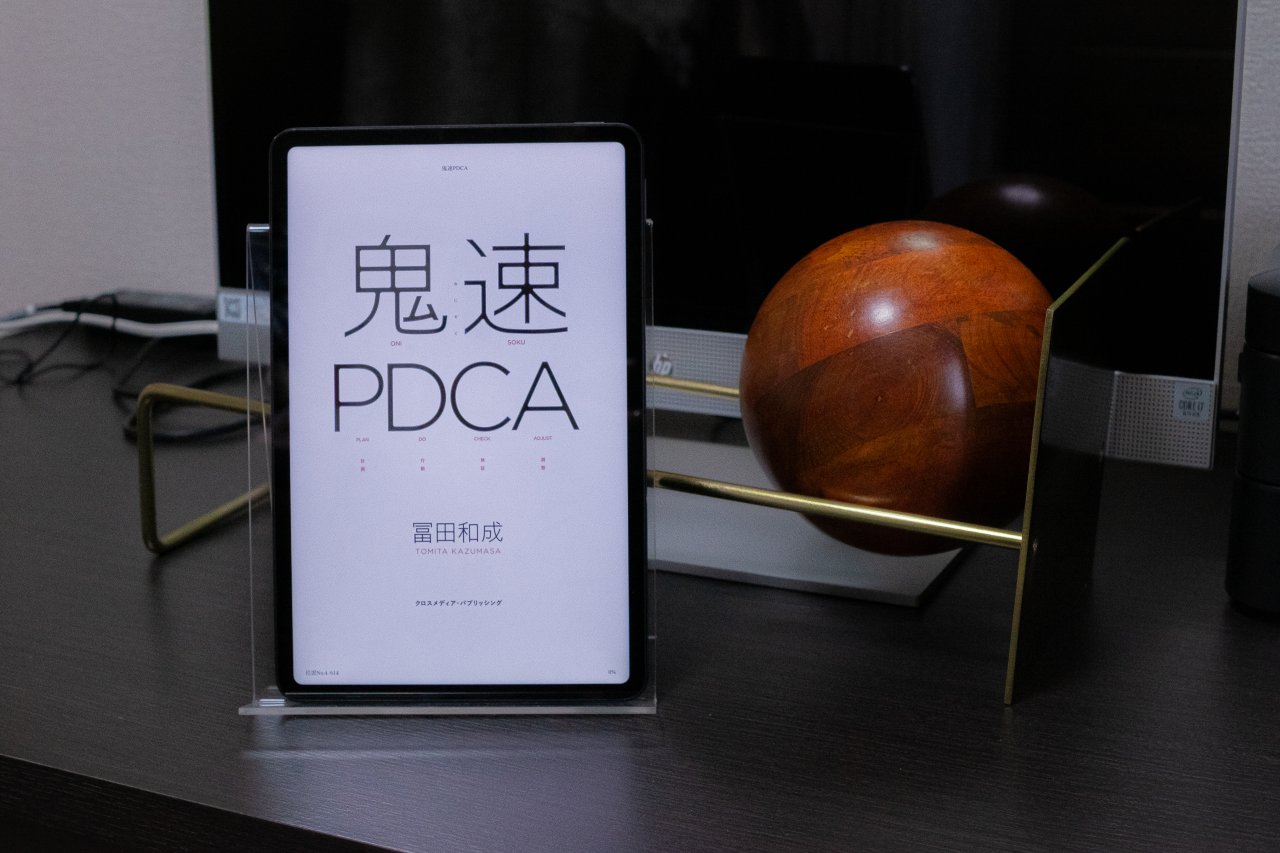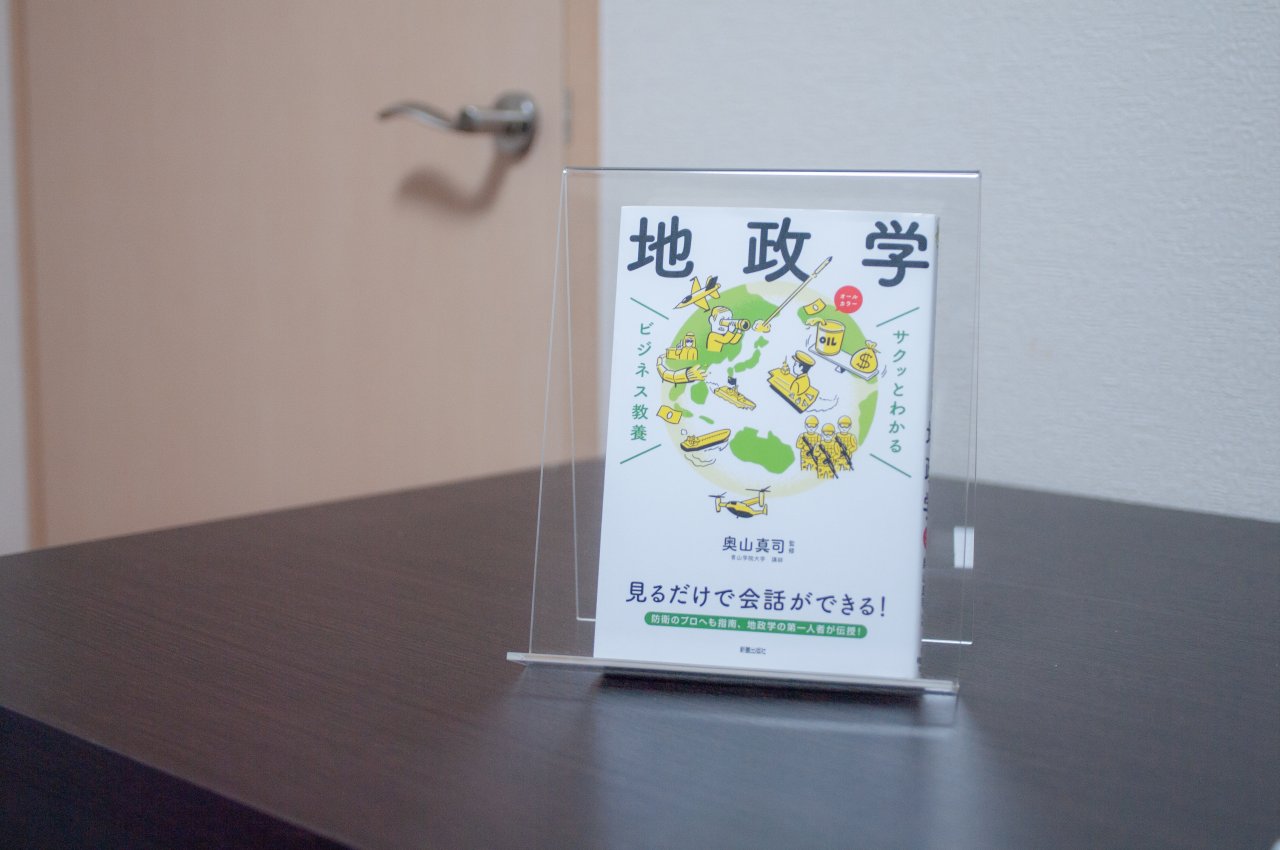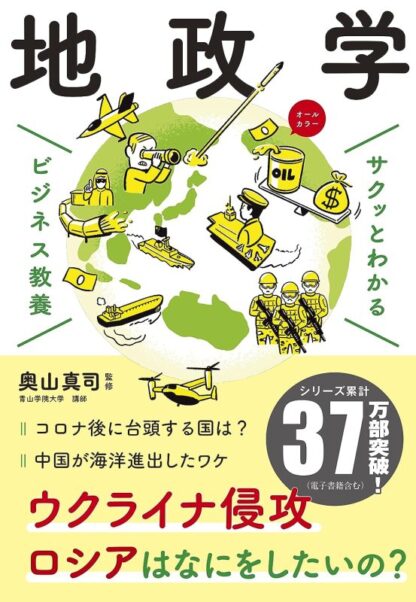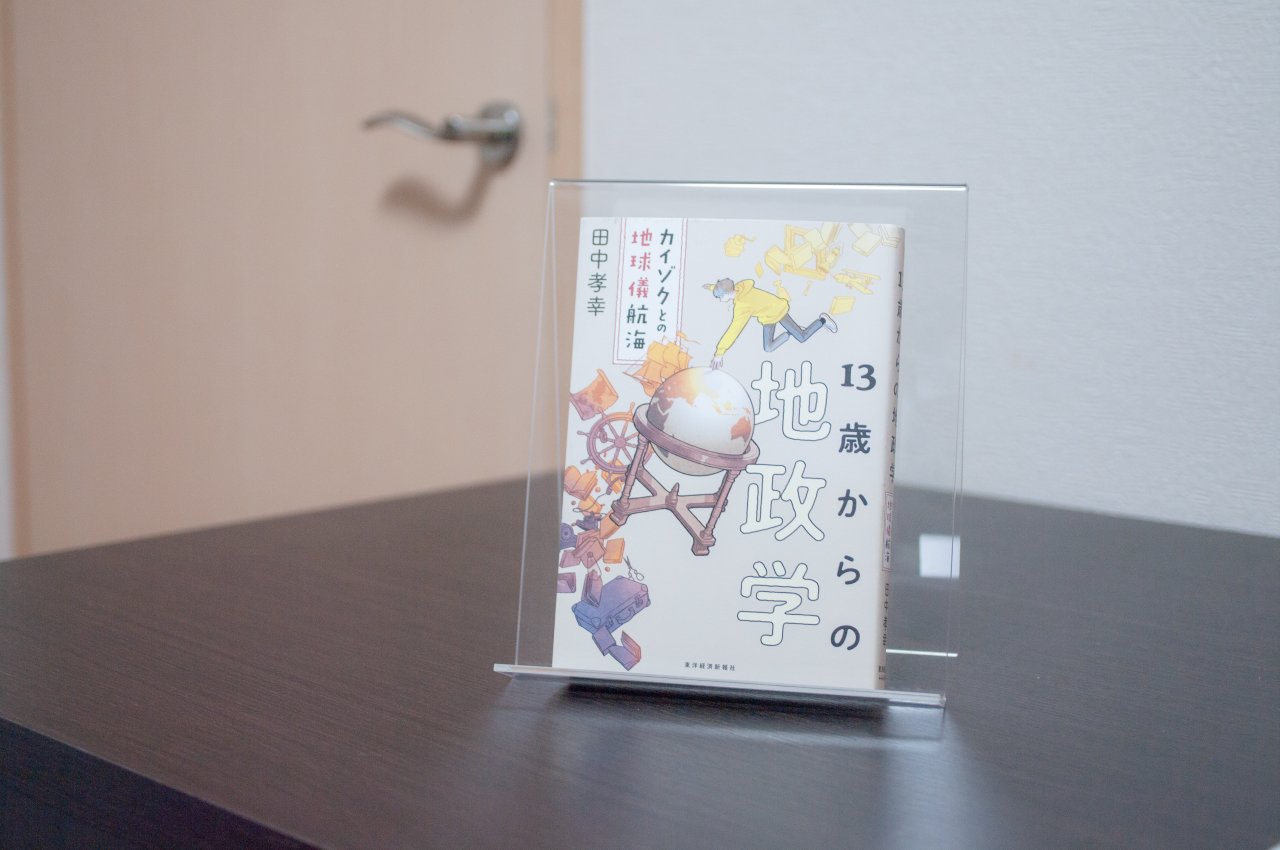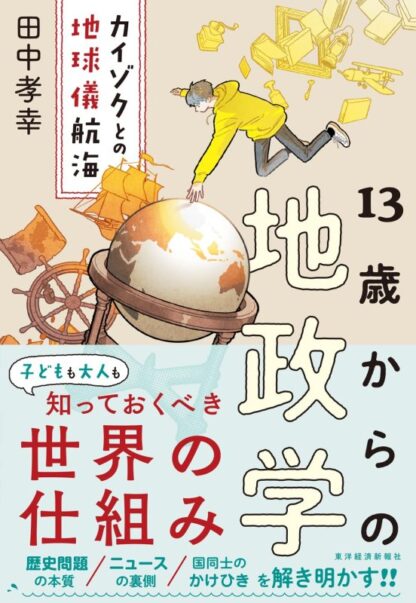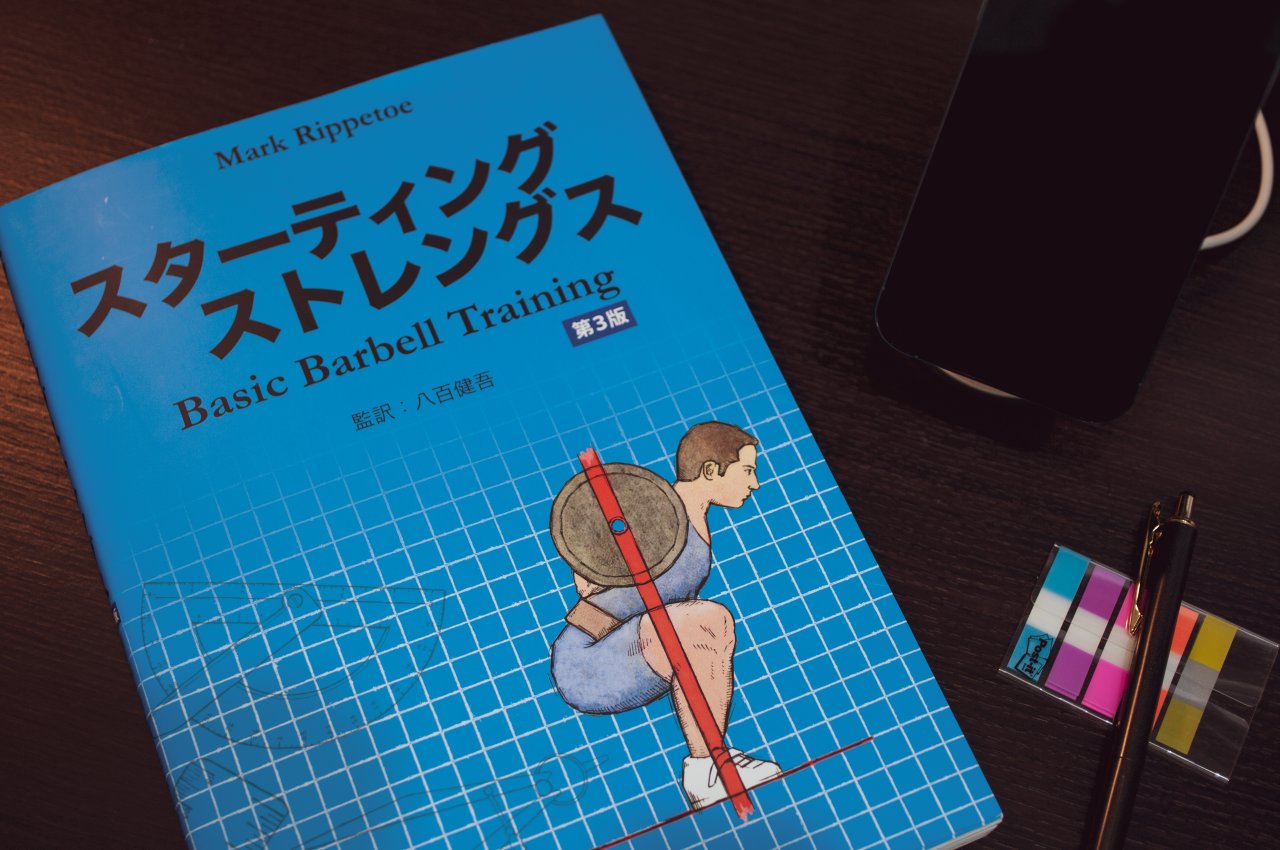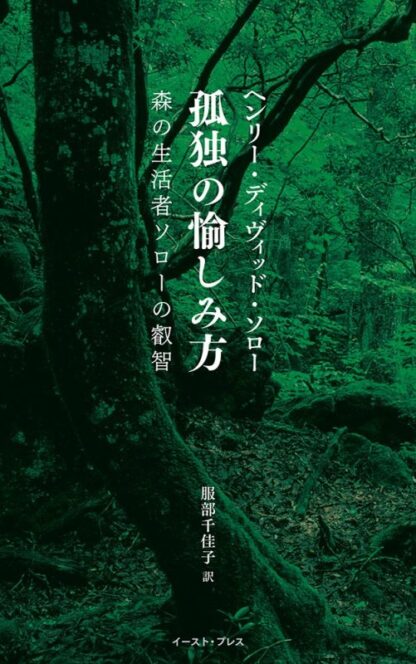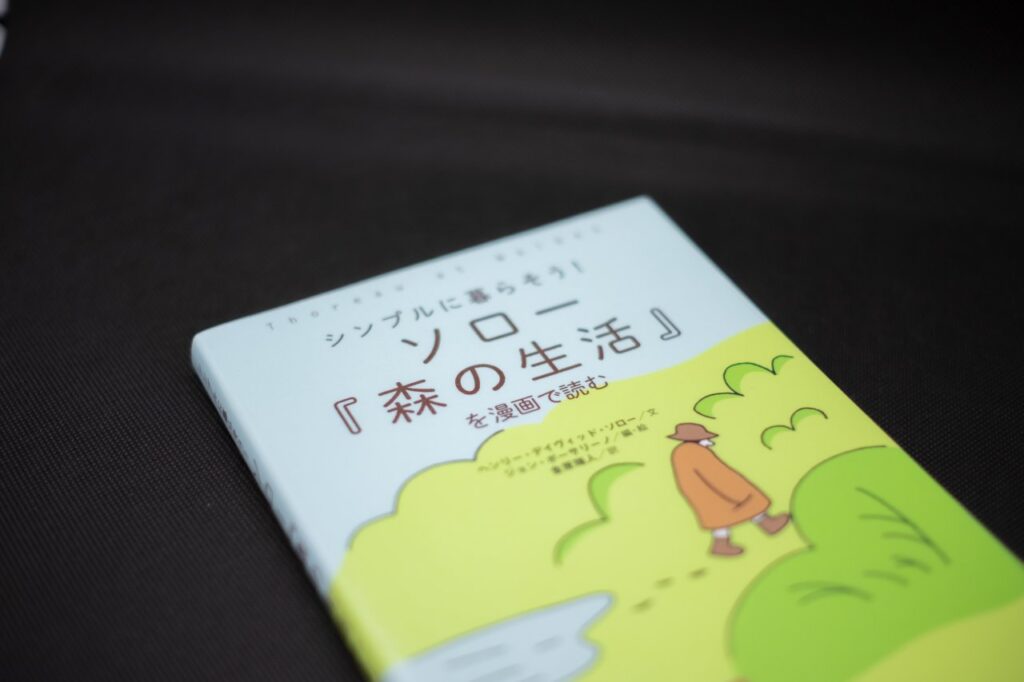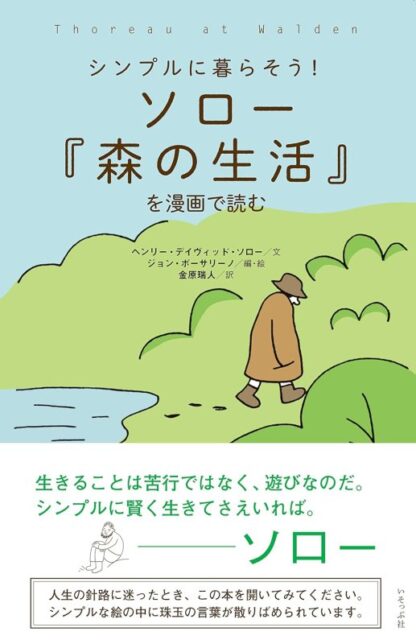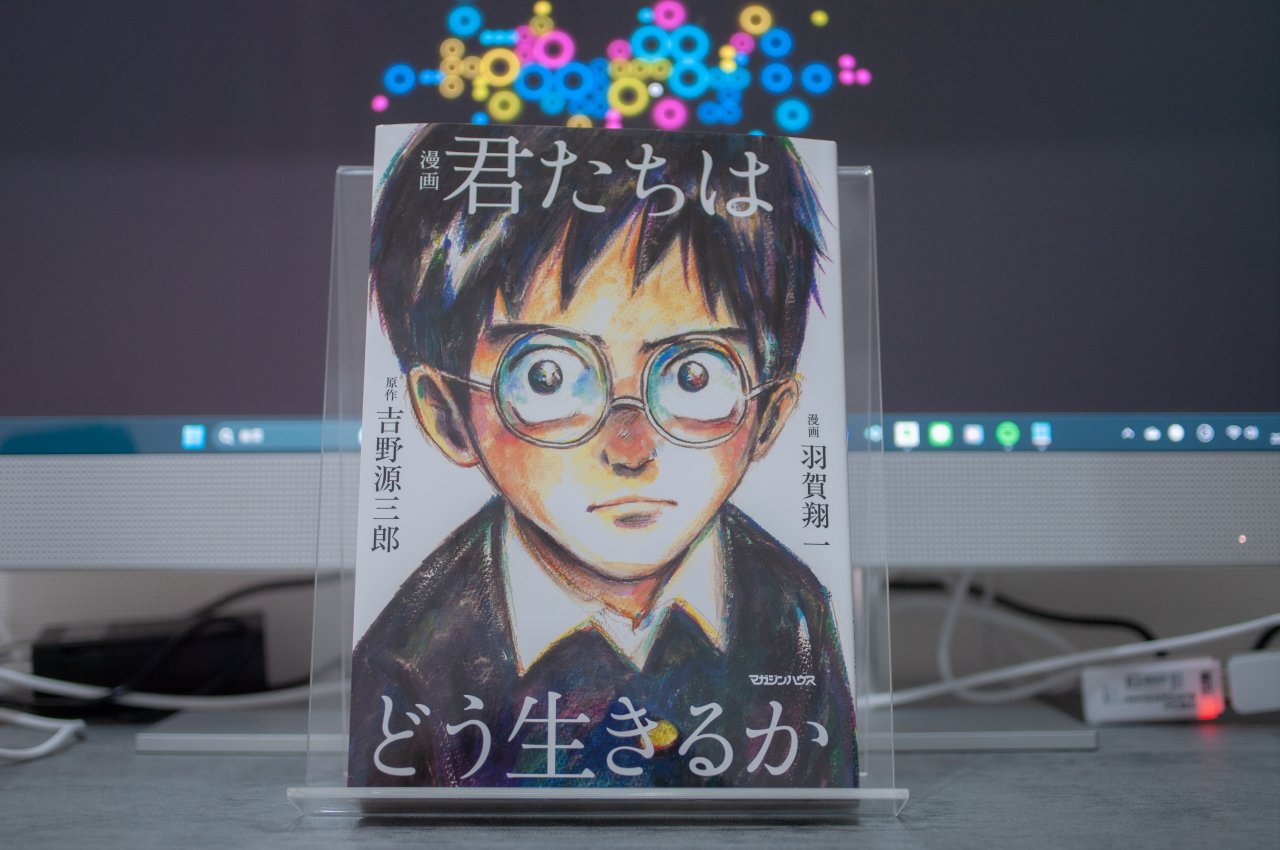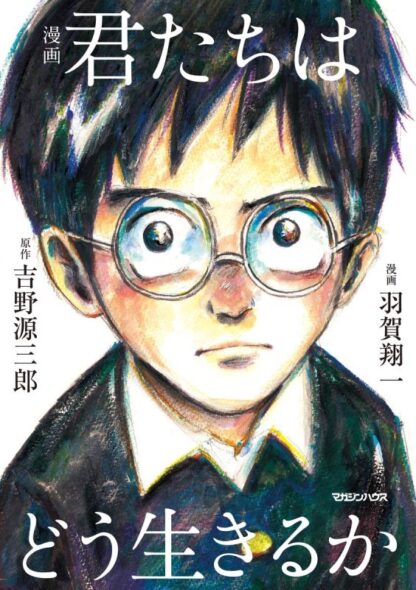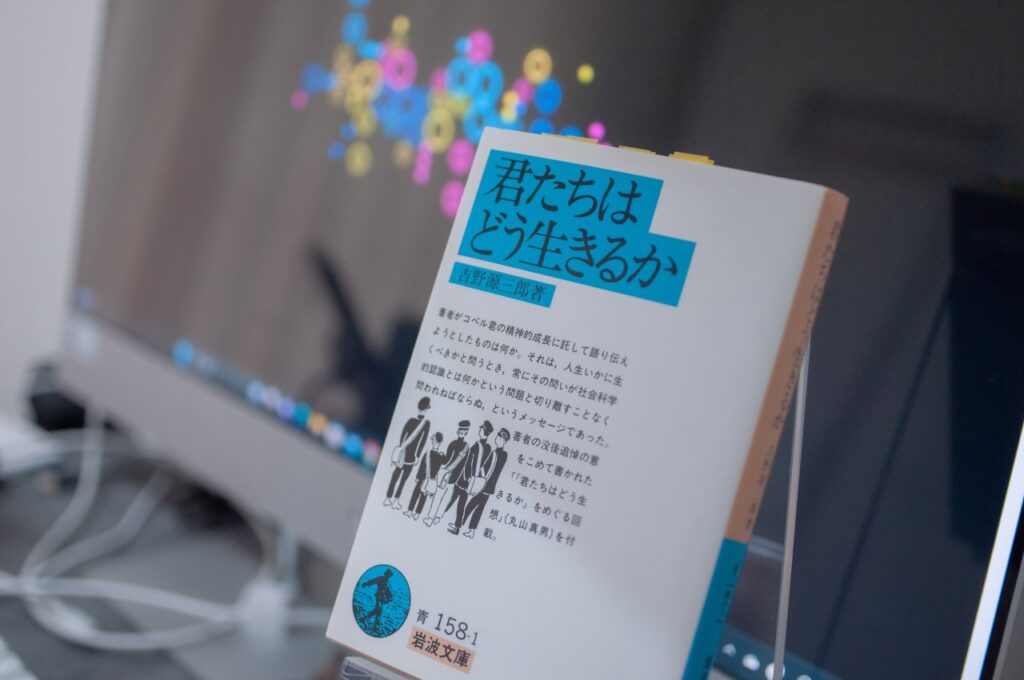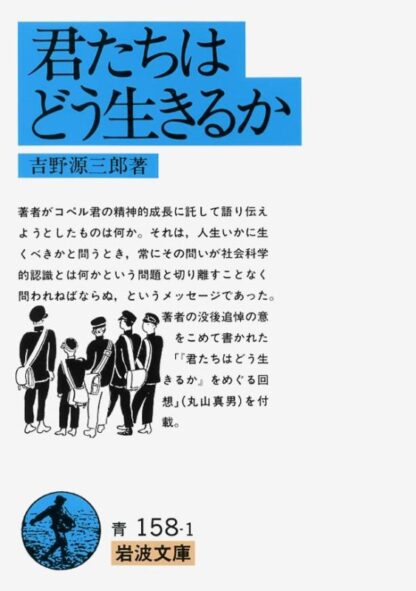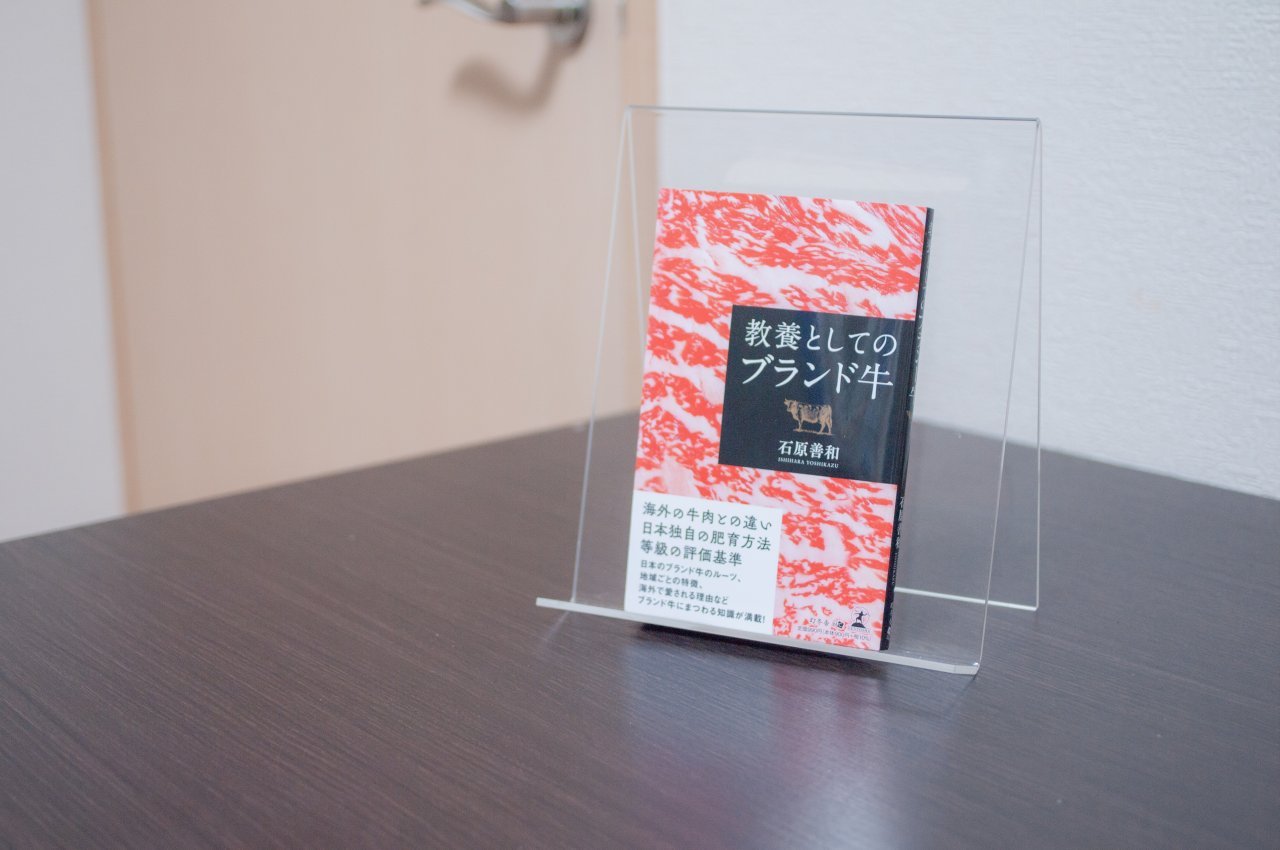
20歳前後くらいのころに北海道の牧場で働いたことがあります。酪農でしたので主に乳牛の飼養管理と搾乳が仕事。
牛乳や牛のことについての基本的な知識はあっても、肉用の牛となるとまた話は別です。牛肉の基礎知識を備えておきたかったので、こちらの新書を読みました。
石原善和
黒毛和牛ブランド「石原牛」生産者、株式会社マル善代表取締役。高校卒業後、超高級和牛「村沢牛」を肥育する村沢牧場で村澤勲氏に師事。2009年に株式会社マル善設立、2017年に1500頭規模へ拡大し、2020年ブランド牛「石原牛」の出荷を開始。2021年「焼肉処石原牛」を福岡でオープン。
概要
日本のブランド牛のルーツから地域ごとの特徴、海外で愛される理由、海外の牛肉との違い、日本独自の肥育方法、等級の評価基準などブランド牛にまつわる知識が得られる一冊。
牛肉の基礎知識と昨今の和牛ブームについて知ることができます。
ブランド牛誕生と発展の歴史
世界の人をも魅了する日本独自のブランド牛、明治以降に改良が重ねられ1944年に和牛の認定が確立。
もともと在来牛は役牛として耕作や運搬などに使役されており、江戸時代までは殺生を禁じる仏教の影響や農業の貴重な労働資源といった考えから肉食は忌避されていました。
しかし滋養強壮として食されてもいて、隠語に馬肉のさくら、鹿肉のもみじ、猪肉のぼたんなどがあります。明治以降文明開化によって肉用牛の改良が奨励されるようになりました。よって和牛の歴史は意外と浅く、その割に急速に発展をとげた産業領域といえます。
著しい和牛改良の伝説スーパー種雄牛が「田尻号(1939~1954)」です。産子数1500頭近く、全体の20%の170頭が種雄牛となり、日本の和牛改良に多大な貢献をしました。2012年全国和牛登録協会の調べによると、全国の黒毛和牛の繁殖雌牛の99.9%が田尻号の子孫であることが証明されています。
300を超えるブランド牛の特徴
食肉通信社 銘柄牛肉ハンドブックによると300種以上、すべて網羅しているわけではないので実際はもっと多くのブランド牛があります。
和牛と表示できるのは黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種とこの4種間交雑種のみ。一方で国産牛に分類されるのは乳用種(主にホルスタイン)や、F1という乳用種と和牛を交配させた交雑種。
4品種あるがその98%が黒毛和種。黒毛和種はサシ(脂肪交雑)が入りやすいからです。つまり和牛=ほぼ黒毛和種といっていい。ちなみにブランド牛=すべて和牛とは限りません。
国産牛は和牛より安価で、肉専用種より早く大きく育つと言ったメリットがありまます。また肥育コストが抑えられて安く、特にF1は肉質も高く和牛に負けず劣らず。
去勢牛は品質が安定しやく枝肉重量も期待でき、一方で雌牛は肉質のきめが細かく味が良いが神経質で肥育難易度が高く品質にバラツキが出やすいといった特徴があります。肥育期間(一般的に月齢8~10か月の子牛を20か月前後肥育)をより長くしたり、与える飼料をこだわったりして地域性や特別性を打ち出します。さらに個体差という生物ならではの特性も加味されます。
日本三大和牛は神戸牛(兵庫)、松阪牛(三重)、近江牛(滋賀)、米沢牛(山口)です。近江と米沢は同列です。これらは世に名前が知られてからの長い歴史があり、300以上のブランド牛の中でも群を抜いています。
例えば神戸牛なら兵庫県産但馬牛の未経産雌牛と去勢牛で、格付け等級がA・B、4等級以上、BMS6以上など、神戸肉流通推進協議会によるブランド定義と基準が設けられています。
知られざるブランド牛の肥育方法
著者の経営や肥育方法などの経験を交えた肥育農家のこだわりが記されています。
濃厚飼料(穀物)と粗飼料(牧草)の割合、成長度合いによる調整、飼料の配合を栄養面や使い勝手から考えること。濃厚飼料は霜降りに欠かせませんが、使うほど生産コストも上がります。生き物である以上個体差はあり、ただ飼料を与えて育つものでもありません。
牛肉は豚や鶏に比べて増体するための生産コストが高く、出荷月齢も長いため肥育コストがかさみ、繁殖は1頭あたり1頭なので20頭産む豚や200以上の卵を産む鶏とは比較になりません。
設備やノウハウ、コスト面から繁殖農家と肥育農家という分業体制がありますが、繁殖から肥育まで一貫して行う一貫農家もあります。
著者は独自の経営手法を一部公開しています。市場で2番手3番手の子牛を仕入れて最高ランクに育ててコストを抑えること、血統だけでなく実際に市場で素質を見極めること。また肥育初期でしっかり腹づくりして、長期的によく食べる牛にすることを心掛けています。このように牛は手をかけるほど応えてくれる、そんな手ごたえが先人の改良を推し進めた魅力の一つかもしれません。
牛肉のランク(等級)の意味を理解し好みの味と出会う
まず等級のABCは量の判定で味に関係ありません。歩留等級と肉質等級は枝肉の第6~第7肋骨間ロース芯の切断面で判定します。部分肉歩留が標準ならB、それより良いならA、それより劣るならCです。もっというと枝肉から骨などを取り除いた大きな肉の塊、部分肉といい、さらに余計な脂やスジを取り除いたものが精肉です。枝肉の70%前後が部分肉、部分肉の80%前後が精肉になります。Aなら72%以上、Bは69~72%未満、Cは69未満です。仮に枝肉500㎏なら、部分肉は350㎏前後、精肉は280㎏前後の計算になります。つまり食肉として利用できる割合が多いかどうかの評価となっています。しかし一般的に和牛でBやCになるケースは少数で、9割はAランクになります。
肉質等級は「脂肪交雑」「肉の色沢」「肉の締まり及びきめ」「脂肪の色沢と質」の4項目それぞれ5~1段階で評価して、その中の最低ランクがついた項目に準じて肉質等級が決定します。つまり5等級はオール5でないとつかない評価であり、一つでも低い評価項目があるとそれに引っ張られて全体の肉質等級が低くなります。このことから、肉質等級も見た目を判断しており味自体は評価していないことが分かるでしょう。格付けは試食ではなく見た目の評価でしかないのでA5が美味しい肉とされてるわけではありません。とはいえその評価が味に比例してるのもほぼ事実なので、評価の高いものが美味しい可能性は高い。
肉質等級にはさらに脂肪交雑の評価に特化したB.M.S.(ビーフマーブリングスタンダード)が定められており、12段階で5等級はNo8~No12に該当。しかしこのNo8とNo12では相当な違いがあるので、同じ5等級でも脂肪交雑の差が大きいことがわかります。
さらなる差別化のポイントとして脂の質の向上、不飽和脂肪酸の含有量が注目されていまする。脂が溶け出す温度の融点が下がり口どけの良い、しつこくない脂になどが好まれるようです。
ブランド牛を堪能するには部位ごとの特徴も欠かせません。地域によって分割方法や呼び名が異なるが、公益社団法人日本食肉格付協会が定める部位の規格では13部位あります。
ネック、肩、肩ロース、リブロース、サーロイン、ひれ、肩バラ、ともばら、ランイチ、ウチモモ、しんたま、そともも、すね
ちなみに焼肉店のカルビという部位はなく、ロースは複数部位の総称です。焼肉のルーツは朝鮮料理でカルビは韓国語であばらを意味し、つまりバラ骨周辺の肉を指していて、肩バラやトモバラにあたります。さらに解釈が広がってバラ系の部位は脂肪が多いので、サシが多い肉=カルビとして提供する店もあります。よってカタロース、リブロース、サーロインなどが特上カルビとして提供されたりもしているようです。一方でロースはカルビと対照的に赤身が多い肉と解釈されています。焼肉店では13部位をさらに小分割してミスジ、ザブトン、シャトーブリアンなど呼称しています。
なぜ日本のブランド牛は世界を魅了するのか?
和牛は世界的にも個性が際立っていて、いうまでもなく霜降りが世界の牛肉の中では稀有なもの。日本独自の改良と肥育技術によって発展してきました。
ではなぜ海外で評価を得てるのに、日本でばかり注目されるのか。一つは黒毛和種が日本固有の品種だから、そして食文化の違いも影響しています。欧米人の食べるステーキの量や頻度では、脂肪が多いと飽きるし日常食品に適していません。逆に日本ではステーキが特別視されるもので、ボリュームよりもご馳走的な味わいを求めて霜降りになったと推察されます。
世界市場でのライバルは海外産WAGYUです。日本での和牛の精液や受精卵はどの国にも輸出してはいけないことになってますが、1970年~1990年にかけて和牛の遺伝子源がオーストラリアやアメリカに持ち込まれた事により、海外でWAGYUが生産されるようになりました。日本独自の和牛改良や肥育技術は簡単に真似できるものではなく、品質が高いものを維持しているが、今後も和牛が世界で通用する産物となるためにブランド力向上などに力を入れる必要があります。
書評
牛のこと、牛肉のこと、等級や牛の呼称など基本的な知識は広く解説されています。
その上で著者の自伝的な側面も交えながら、ブランド牛の成り立ちや肥育技術などちょっと踏み込んだ話まで展開されています。著者が石原牛というブランド牛を保有していることもあって、本書からのPRを感じなくもないですが、牛のプロとしての内容は参考になって説得力もあります。
日本の和牛が世界的に見ても優れた技術と品質を有しており、それを誇りに思っているのが随所に表れていました。そのブランド力を維持していくことも農家の務めであり、我々消費者にも知っておくだけで意味があると訴えかけています。
私のような庶民には和牛なんてそう口にすることはありませんが、いざ何かのご馳走や、ふるさと納税の返礼品選びなどに、最低限の知識があるだけでも選択の幅が広がりそうです。
教養としてのブランド牛
石原善和
35年以上にわたって和牛の肥育を生業とし、自らもブランド牛を立ち上げた著者が、生産者ならではの目線も盛り込みながら、
ブランド牛にまつわる知識と魅力を幅広く語っています。より深くブランド牛を味わい尽くすための、「教養としてのブランド牛」を楽しめる一冊。